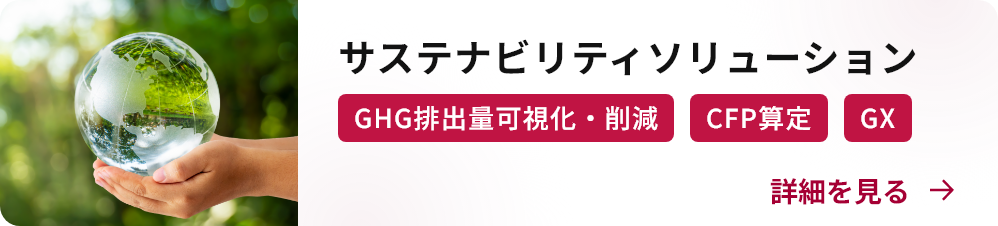新入社員の皆さん、長瀬産業、NAGASEグループ各社への入社、誠におめでとうございます。
オンラインも含め、91名が参加しています。皆さんをグループの一員として迎えることができ、大変嬉しく思っています。近い将来、国内外のさまざまな場面で皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしています。
皆さんは昨日までは「アマチュア」、今日からは「プロ」です。お客様、社会、株主、従業員などのステークホルダーに商品やサービスを提供し、その価値を認めてもらい、見返りとして報酬を頂くのが「プロ」です。皆さんはまだ何も提供していませんが、私たちは皆さんの将来の可能性に大きな期待を寄せています。会社にはいろいろなタイプの仕事があります。営業、製造、研究開発、法務、業務。どの仕事も、一つでも欠けてしまうとNAGASEの経済活動が機能停止する重要な仕事です。責任感、使命感、向上心、そしてプライドを持って、プロとして仕事に向き合ってください。
私たちは今、未だかつてない変化の時代に存在しています。
一つ目の変化は、「環境への意識の高まり」です。以前は、企業がお金を儲けること、すなわち経済活動をすることと、環境問題や社会課題にコストをかけて取り組むことは、切り離すことができた「トレードオフ」の時代でした。
しかし今は、社会課題や環境問題に取り組んでいない企業は経済活動、つまりお金を儲けることが許されない「トレードオン」の時代に入っています。
二つ目の変化は、「生成AIの誕生と実用化」です。まさに技術イノベーションによる変化の時代です。
私たちの生活が大変便利になる一方、生成AIを使うために沢山のデータセンターがつくられ、日本はもちろん世界中で電力不足が深刻な社会問題となっています。また、人間の労働がAIに置き換えられ、雇用機会が減少する時代にもつながっていきます。
そして、三つ目の変化は「経済安保」、米中関係やウクライナ・ロシアの戦争、中国・台湾問題、イスラエルを中心とした中東情勢といった地政学リスクなど、日々が有事の時代に突入していることです。
一年前の常識ですら過去のものとなり、新しい常識が猛スピードで形成されています。少し前までは、過去の成功体験を踏襲していれば生き残ることができました。今は違います。過去の成功体験への盲信が現実を直視する目を曇らせ、誤った判断や機能停止をもたらします。大きな会社でも対応を誤れば、潰れてしまう時代になっています。
一方で、変化はチャンスでもあります。これだけの大きな変化はまさに何十年に一度のチャンスです。リスクをチャンスに変えるためには、常にトランスフォーム(変革)し続けることが必要です。「一緒に成し遂げたい」という情熱をもって、一日も早く先輩たちに溶け込み、変革のドライバーになってほしいと期待しています。
このような時代だからこそ大切にしなければならないのが、NAGASEの経営理念です。私たちには「社会の構成員たることを自覚し、誠実に正道を歩み、社会が求める製品とサービスを提供し、会社の発展を通じて社員の福祉の向上と社会への貢献に努める」という、すばらしい企業理念があります。これこそが193年続くNAGASEグループのパーパスであり、私も含めすべての社員が意思決定や是非を判断する軸に迷ったときに立ち返る場所です。
この会社の歴史について少しお話したいと思います。NAGASEは1832年に京都で着物用の染料問屋(当時は紅花の赤)として創業しました。2032年には200周年を迎えます。1900年代には、化学先進国である欧米の大手化学メーカーからの輸入ビジネスを開始し、1970年代には国内での海外メーカーとの合弁で製造業を立ち上げ、その後自社でもメーカーをいくつも立ち上げています。1990年代には自社で研究所をつくり、バイオの研究に力を入れてきました。2010年以降はM&Aを活用して事業拡大を進め、ナガセヴィータ(旧林原)やPrinovaをグループジョインさせ、企業価値を拡大してきました。また最近では、旭化成ファーマ社の酵素診断薬事業、米国SACHEM社の買収を発表しました。また、新事業の創出ならびに成長機会の獲得を目的にコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)によるスタートアップ企業への投資も行うなど、時代に合わせてトランスフォームしてきています。
この190年以上の間に当社が積み重ねてきたものとは一体何でしょうか。日本企業の平均寿命が約30年と一般的にいわれる中、NAGASEが190年以上続いていることには理由があります。それは紛れもなくNAGASEに対する「信用」です。そして、世界中の人や企業にリーチできる「ネットワーク」です。この2つこそが、190年積み重ねてきたNAGASEの財産といえます。ビジネスの世界で、スタートアップ企業が苦労し、努力しても簡単には手に入らないものが「信用」です。この最も大切な「信用」という財産を、新入社員の皆さんは無償で引き継ぐことができるのです。
ところで、「信用」とは何かと考えたとき、それはシンプルに「約束を守ること、噓をつかないこと」だと思います。ビジネスのすべては、約束を守ることで成り立っています。これを190年間続けてきた、まさに誠実に正道を歩んできたからこそ、NAGASEはすべてのお取引先様から、「何か困ったらNAGASEに聞いてみよう」と言っていただける現在の姿になっています。近い将来、皆さんにはこの「信用」を活用し、世界中で大きな事業に挑戦していってくれることを期待しています。
最後に、私の経営哲学と皆さんへのアドバイスで締めくくりたいと思います。
私の経営哲学は「ひとと仕組みをつくる」ことです。
「人的資本」という言葉がありますが、私はこの言葉には違和感を持っています。ひとはモノでもお金でもなく、将来を見つめ、未来をつくる存在であり、他者との関係の中で成長し、資本を生み出すのがひとだと思っています。NAGASEにとって、「ひとは命であり、魂」です。ひとを育てることがNAGASEの成長に直結していると信じています。ひとを育て、NAGASEグループが持続的に発展する仕組みをつくることが、私にとって最も重要な仕事であると考えています。
ここで、私が実践してきた成長の秘訣を皆さんにお伝えします。
■突き詰める
誰でもできる仕事こそ、誰がやったかで一番差が出るものです。最初は職場で簡単な仕事から任されます。レストランならお皿洗い、これは誰にでもできる仕事です。しかし、お皿洗いでも誰もやらないレベルまできれいに洗えば、誰も想像できないレベルまで工夫し、丁寧に整頓すれば、もはやそれは「あなたにしかできない仕事」になるのです。
洗った後のグラスや洗い場の状態を見れば、「あっ、今日はあの人が洗い場を担当してくれたんだな」と分かるのです。ひとも、会社も、そういうところをよく見ています。そして、そのひとに「次はこれを任せてみよう」と、次のチャンスが訪れるのです。そして、それをまた「自分にしかできない仕事」になるよう、突き詰めてください。
地味なように聞こえますが、これが、私の座右の銘である「一燈照隅」です。メモの取り方、書類の準備の仕方、アポイントの取り方一つとっても、すべてにおいて手を抜かない、相手の気持ちになって工夫する、与えられたあなたの役目を誰もできない領域まで突き詰めれば、それはもはやあなたにしかできない仕事になるのです。そして次々と依頼が増え、大きな仕事を任してもらえるようになります。
「一燈照隅」、つまり皆さんそれぞれの光が照らす範囲を突き詰めて、自分の仕事にしていけば範囲はどんどんと広がっていく。私はこれまでもそうしてきました。そして今の私の照らす範囲はNAGASEグループ全体まで広がっています。ぜひ、皆さんも今日から実践してください。
■人、皆師なり
2つ目は、「人、皆師なり」という考え方です。私は学生時代化学を専攻していたこともあり、人生は壮大な実験場だと考えています。すべてに学びがあり、学びたい人はいくらでも学べます。まずは「学びたい」と常に思うことから始めてください。常にこう思うのは大変なことですが、気を抜かず、朝起きてから夜寝るまで、「学びたい」と思うように努めてください。
どのようにして学ぶか、ですが、皆さんにはこれから沢山の人との出会いがあると思います。その時に、自分と人とを比べてしまうのであれば、その思考はまずやめましょう。「マウントを取りたい」という欲求があれば、捨ててください。人に上下はありません。年齢も、性別も、外見も、能力も全く関係ありません。どんな相手からも「学びたい」という気持ちを持ってほしいです。敬意を持って、相手の話を最後まで聞き、すべてを受け止めると、本当に多くの気づきを得ることができます。すべての人があなたの先生なのです。警備員さんも、コンビニの店員さんも、先輩も、たとえ子供であっても子供の感じ方や考え方を教えてくれる先生なのです。先入観を捨て、まず最後まで相手の話を聞いていけば、あなたが今まで知らなかった異質な主観や思い、意見を学ぶことができます。ぜひこれも実践してみてください。
今日、この入社式に参加している91名は、今後20年、30年経っても皆さんの同期です。生涯を通してかけがえのない仲間になります。ある時は相談し、ある時は支え合い、そしてある時はライバルにもなるでしょうが、是非ともこの絆を大切にしてください。
皆さん、本当にNAGASEに入社してくれてありがとう。改めて、おめでとうございます。そして、健康面、自己管理を徹底することを忘れないようお願いします。
最後にもう一言 、皆さんはすでにNAGASEの「信用」と「看板」を背負っている社会人です。
自覚を持って行動するようにお願いします。以上、私からの挨拶とさせていただきます。
2025年4月1日
上島宏之